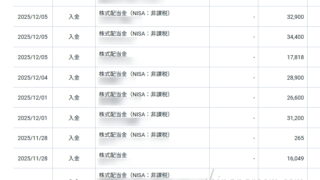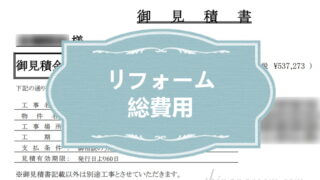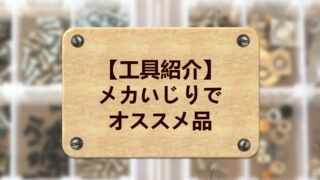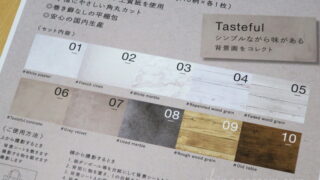モーター故障のおもちゃを修理で復活

ハローキティの『マジックドレッサー』(1999年製)のジャンク品を入手しました。
ジャンク内容は、鏡が自動開閉しないというモーター故障によるものでした。
- 全ての機械に言えますが、分解するとメーカー保証が無くなります
- 分解・修理・改造は全て自己責任でお願いします
目次
Youtube動画はこちら
今回のおもちゃも、アンパンマン自販機同様に大きかったので、背景画がちょっとツギハギな感じになっちゃってます。普通に壁の前に置いて撮影したらいいのでは…という話でもあるのですが、撮影環境的には窓に近い場所の自然光で撮りたかったんですよね。
鏡と向かい合う形になってしまうので、余計なものができるだけ映りこまないように、そこは注意しながら撮影してみました。鏡に映るキティもわかりやすくなったかなと。
色分けや文字入れなど色々してみたので、ポイントごとに皆さんに伝わっているといいなと思います。
また修理工程を除いた、おもちゃだけの紹介動画も作りましたので「おもちゃのギミックが知りたい!」という方には下記の動画が面白いかなと思います。ボタン操作以外でも遊べる様子を見てみて下さい。
電池の液漏れ・リード線使用について
電池の液漏れもしてはいたのですが、音自体は出ていて不可動品とまではいかなかったので、液漏れについては今回はあまり大きく取り上げませんでした。
ただ、今回電池ホルダーで細い線のような金属が使用されていたのが断線していました。使用されていた電池ホルダーが、+-それぞれ独立していたんですよね。最近の電池ホルダーは隣同士+-がくっついたプレートを使用されていることが多いです。
この電池ホルダーは全部が独立していて直列を繋ぐ必要が出てくるので、あの細い線が使用されていたようです。それをリード線に付け替えたわけですが、電流速度を考えるとリード線でよかったのかな…と考えるところはあります。動作確認では特に遅延というものも感じませんが、修理が上手い方なら違う線を使用しているのかなと思います。
電池ホルダーの錆び落としについては、ヤスリやお酢などの方法がありますが、注意点もあります。今回電池ホルダーの錆び落としの際、パーツが外れてしまったので、動画内にちらっと映っていますがホットボンドでくっ付けています。
過去の記事『錆び落としはどれがいいの?』の項目で、何を使用するかの参考にしていただければと思います。

モーター修理は慎重に
分解せずに接点復活スプレーをかけていますが、これは簡単ではありますがやり方としては少々荒業に近い方法です。
少量ずつかける理由としては、モーターによっては内部に使用されている樹脂を溶かしてしまう恐れもあるためです。仮に溶かす恐れのある樹脂が使用されていないにしても、油をたくさん入れ過ぎてオイル漬け状態になるのもよいとはいえません。
油を入れた後に色々な方向に傾けるというのは、少量の油で錆びているであろう箇所に巡らせるためです。錆びが怪しいのは底の部分あたりかなと思いますが、保管されていた環境にもよるかと思います。
傾けているうちに、油が穴から出てくるのでそれを出来るだけ取り除きます。中途半端にしか油を取り除かなかった場合、後から流れ出てきて余計な箇所に油が付着してしまいます。
少量の油で試してみてまだ上手くいかない場合は、少しだけ量を足してみて…それでも上手くいかなかったら、最終的には分解になるかもしれません。モーターを分解するには、左右の爪を引っかけて開けるという方法があります。
スピーカーの錆びつき
スピーカーは古い玩具では音割れは起きやすく、その場合は錆びが出ている可能性が高いです。
結構錆びていると動画のようにあんな感じの見た目になります。パッと見ただけでは分かりづらい錆びのケースもありますが、よく見てみると錆びている個所が発見できるかと思います。
音割れが酷いスピーカーを交換すると、おもちゃによってはクリアで綺麗な音声に戻るので、驚くこともあるかと思います。今回のは見違える程とまではいきませんでしたが、それでもやはり良くはなりました。
色々ジャンク品の分解をやっていると、ネジ類の他にスピーカーも得られたりするので、そういった中からパーツを使用しました。検索してみると同サイズのスピーカーは割とヒットするのですが、価格が少々高かったりもするので、分解ついでにスピーカーもゲットするのがお得ですね。
まとめ
今回はモーター故障を修理するというものでしたが、きっと皆さんが予想していたものほども難しくはないものだったかなと思います。
どれもこれも錆びが原因…という感じがしてしまいますが、錆びへの対処方法がわかると、直せる玩具の幅が広がるかなと思います。
また古い玩具を修理したら、こうしてまとめてみたいと思います。